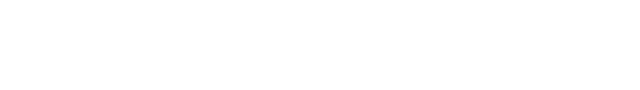診療案内
患者様の声に耳を傾け、わかりやすいご説明をし患者様に納得して頂く医療を心がけます。
診療内容
一般的な内科系疾患
風邪、扁桃腺炎、発熱、疲れ・疲労、だるい、体重減少、立ちくらみ、食欲不振・減退、花粉症、蕁麻疹など
消化器科系疾患
腹痛、嘔吐、胸やけ、食欲不振、膨満感、下痢、下血、便秘
造影超音波
超音波にも造影剤を使えることをご存じでしょうか?
まずは超音波のお話をします。超音波は人の耳には聞こえない音です。魚群探知機は超音波を利用しています。超音波探触子からビームをだし、反射したビームが探触子に戻るとはじめて超音波画像になります。空気が存在しない臓器、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓が超音波検査のいい対象となります。
一方、空気中ではビームが散乱してしまうため、空気の向こう側は観察することができません。空気を含有する肺や消化管、肺や消化管などに含まれる空気に邪魔される部位は超音波検査のいい対象とはなりません。
第二世代の超音波造影剤ソナゾイドは、2007年に日本が世界に先駆けて「肝腫瘤の診断」に保険適応となりました。これは赤血球よりも小さなガスなのですが、肝臓や腎臓には負担がなく、肺で分解され呼気として排泄されます。腎機能が悪い方、喘息のある方、妊娠されている方、造影CTや造影MRIの造影剤にアレルギーのある方にも使用可能です。非常に安全性が高く、大きな副作用はなく、造影CTや造影MRIよりも安価です。
さらには造影CTや造影MRIと同様に動脈相、門脈相、晩期相、後血管相でそれぞれ肝腫瘍を評価できます。血管腫、限局性結節性過形成(FNH)等の良性腫瘍(腫瘤)、肝細胞癌、肝内胆管癌、転移性肝癌等の悪性腫瘍診断の精密な検査として使用できます。また磁気センサーを用いて、造影CTや造影MRIの座標と超音波の座上を一致させ、CT/MRIで指摘された病変を造影超音波で検出する融合画像という手法もあります。
超音波自体の弱点としては脂肪組織ではビームが減衰してしまうため非常に太ったかたや、高度の脂肪肝の方では体表から深部にある病変の評価が困難になることです。
当院では造影超音波、融合画像を実施し、より精度高く肝腫瘤の診断が可能です。